AI要約:『事例でわかる伝聞法則』の評価と特徴
本書は、刑事訴訟法最大の難所である「伝聞法則」を、実務家の視点から徹底的に噛み砕いた、苦手克服のためのバイブル的演習書です。
主な特徴とメリット
-
「立証構造」を把握するメソッド: 弁護士である著者により、法廷で検察官の立証を吟味する際の実務感覚が伝授されます。受験生がつまずきやすい「内容の真実性が問題か否か(伝聞・非伝聞の区別)」を、立証趣旨との関係(立証構造)から見抜く力が身につきます。
-
「伝聞ノック」による基礎能力の養成: 1行程度の極めてシンプルな短文事例からスタートし、段階的にステップアップしていく構成です。論点以前の「当たり前の処理」を繰り返すことで、複雑な司法試験の問題でも解説がスラスラ理解できるレベルの基礎体力がつきます。
-
圧倒的な薄さとタイパの良さ: 非常に薄い書籍であり、集中すれば短期間で読了可能です。それでいて網羅性も高く、自然反応供述などの高度な項目までカバーされています。
-
司法試験過去問への架け橋: 第5章には司法試験の過去問解説も収録されています。本書で本質的な理解(最短ルート)を確立した後に過去問へ挑むことで、難解な伝聞問題が「実務家にとっては当たり前の基本の組み合わせ」に見えてくるようになります。
留意点
-
定義の補完: 徹底して「具体的なあてはめ・処理」に特化しており、理論的な解説は最低限に留められています。伝聞の正確な定義については、必要に応じて他の基本書や判例集で確認し、論証として固めておく必要があります。
-
演習の継続: 本書を終えただけで過去問が即座にスラスラ解けるわけではありません。本書で得た「武器」を手に、実際の長文事例で事実を拾い上げる訓練を積むことが合格への王道です。

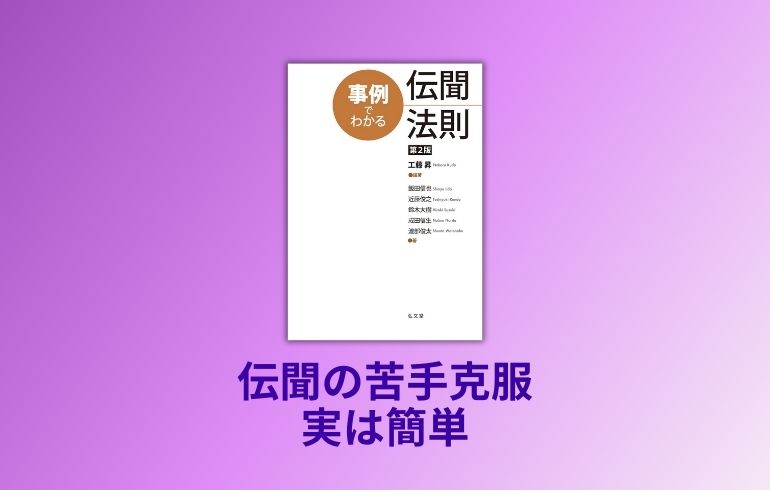

レビュー
3
伝聞はコレ
伝聞の予備校講義や動画を見るよりも、ストゥディア刑訴くらいの軽めの本でひと通りやったなら、あとはコレを読み、演習するのみ。こんなによく出来た本はない。
実務に出ても混乱したらこの本を読む。
続きを読む 閉じる
伝聞のマスターはまず、苦手意識の払拭から。まずはここから盤石な基礎能力を。
1 司法試験への有用性
端的に結論を申し上げます。司法試験への有用性はあります。まず、司法試験の刑訴法の伝聞出題率は群を抜いて高いです。超必須事項なのです。したがって、伝聞についてまとめた書籍はそれだけで有用性があるといえるのです。
ただ基本書のように難しく書かれていては心が折れます。まずは少ない文章の短文問題で少しずつ腕ならししていくと良いと思います。その手助けになるのが本書です。まずは、供述証拠とはなにか、からスタートしていた印象です。そこから伝聞とはなにか、これは伝聞か非伝聞かを区別して議論していたイメージです。小さなところからステップアップしていく感じがあるので、ひとつひとつ咀嚼しながら小さな理解を積み重ねれば、難しい伝聞の問題も解ける「基礎能力」が身につけるようになると思います。
伝聞例外は論証でおさえられるけど、伝聞・非伝聞の区別が実はかなり難しいんですよね。角がたつので名前は伏せますが某有名予備校の基礎講座は丁寧に解説していなかったような・・。ロー(既習)では伝聞・非伝聞の区別は当たり前という前提で丁寧に説明もされていないし・・。なので、本書は必須といえるのかなぁと。
薄いくせに割とレベル高いところや網羅性も高いなと思うところもありました(自然反応供述が記載されるなど)。なのでとりあえず本書を一通りやれば、過去問などの問題がすぐ解けなくても、解説を読んで理解することぐらいはできるのではないか、とは思います。
ただ勘違いしないでほしいのが、これだけで過去問はスラスラ解けないということです。過去問の伝聞って本当に難しいんです。まず、問題の難易度が難しいだけでなく、時間がなくて満足に書けない人がほとんどだと思います。なので、本書をそれなりにできるようになっても、過去問レベルの問題はスラスラ解けないのは当たり前なので安心してくださいね。
逆をいえば、過去問の問題の解説が理解できれば、割と同じことを繰り返していると感じがするので、解けるようになると思います。最短ルートだと、本書→過去問ですね。王道だと、本書→法律の雑誌の伝聞に関する記事→過去問ですかね。
伝聞例外の論証を大量に覚える前に、本書で伝聞・非伝聞の本質について探ってみてください。
2 わかりやすさ・読みやすさ
特別にわかりにくいとか、読みにくいというのはありません。上記1で言及した通り、短い文章問題(1行程度で終わるものも!)のあとに、丁寧めに解説しています。私の読んだ学習状況(ローの刑訴で伝聞が苦手すぎてテストでやらかした状況)でも理解できました。だから、あなたも大丈夫です。
3 網羅性
伝聞について一通り書いてあるんじゃないでしょうか。範囲で著しく説明が抜けているという印象はありません。ただ、何度も繰り返し述べている通り、これだけで過去問をすぐに解けるようにはならないので、理解したら過去問を解いてみてください。
4 コスパ
コスパはいいですよ!まず、手にとってみて薄い!これなら1週間あれば楽勝でしょう。1日で終えることもできますが、そんな急いでやる必要はなく、じっくり一つずつ噛みしめるように進めると良いと思います。伝聞は理解が重要なので。
続きを読む 閉じる
伝聞の苦手克服は実は簡単
伝聞法則に特化した参考書。
著者は弁護士であり,実はこれが本書の最大の特徴。
受験生が伝聞法則につまづく最大の理由は,私見では,立証構造が把握できていないために,供述の内容の真実性が問題となっているか否かの判別ができないことにある。
本書は弁護士,つまり法廷で検察官の立証構造を吟味する立場にある者による本であり,大げさにいえば,立証構造を把握できるようになるメソッドを知り尽くしている者といえる。
本書はまず,「基本書を見てみても,実際の裁判で具体的にどういう供述が伝聞になり,あるいは非伝聞になるのかといった具体的なことは今ひとつわからない」「学生にこの壁を越えてもらうには,とくかく擬似的にでも法廷における実務体験をしてもらうしかない」(はしがきⅱ頁)と問題提起する。そして,その解決のために,「いわゆる論点を含まない事例も多く検討し」「実務感覚を擬似的に体験できるよう,事例問題を中心に極力具体的な記述を心がけ」ている(同ⅲ頁)。
確かに,手続法の学習のポイントは論点を含まない,平常時の手続の把握にあり,論点という,いわば法廷における限界事例のみを学習すると,かえって全体像の理解が遅れることになる。
本書は,立証構造を把握するためにシンプルな事例問題を繰り返す本であり(「伝聞ノック」(同ⅱ頁)),これにより,司法試験において出題された事例が,どのパターンの立証構造の理解を問うているのかの判別が容易になる。本書の第4章までをこなせば,司法試験で聞かれている伝聞法則が,弁護士等の実務家にとってはあたりまえの,単純で基本的なことであることが理解できるようになる。本書の5章は司法試験問題(H20ないし23,25,27ないし30,R3)の解説である。
なお本書の事例の解説の中には,極めてシンプルなものもあるが,事例問題を最初から検討していけば,どういう理由でその結論が導かれたのかの理解に困ることはない。
本書は「理論的な解説は最低限にとどめ」ている(同ⅲ頁)ことから,伝聞証拠の定義については後藤昭著「伝聞法則に強くなる」等の書籍を参照することも考えられるが,本書と用いている単語の意味に違いがありうるので,注意されたい。本書のみで伝聞証拠の定義を学ぶことには慎重であるべきである。
続きを読む 閉じる