
アクセス頂きありがとうございます。
法書ログは、法律書籍の口コミサイトです。
先輩たちのリアルの体験談に基づいた口コミがたくさん投稿されています。
是非、勉強に役立ててください!

口コミを閲覧する方法は下記画像をクリックしてご確認ください。
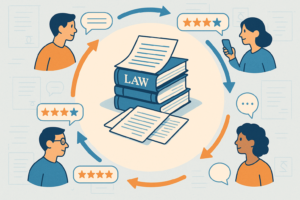
AI要約:『憲法 事例問題起案の基礎』の評価と特徴 本書は、知識はあるのに「憲法の答案をどう書けばいいか分からない」と悩む受験生の間で、「隠れた名著」として語り継がれている一冊です。 主な特徴とメリット 「お作法」と「型 […]
法律書籍のランキングです。科目ごとのランキングを公開しています。
AI要約:『刑法総論の悩みどころ』の評価と特徴 本書は、刑法学界の第一人者である橋爪大三郎教授が、実務や試験で問われる重要・発展的論点を深掘りした珠玉の解説書です。単なる学説の羅列ではなく、議論の「土俵」を整理し、筆者の […]
AI要約:『民法の基礎2 物権』の評価と特徴 本書は、難解な物権法を圧倒的な読みやすさで解き明かした、初学者から司法試験受験生まで広く支持される定番の基本書です。 主な特徴とメリット 圧倒的な分かりやすさと構成: 具体的 […]
AI要約:『刑法演習サブノート210問』の評価と特徴 本書は、刑法総論・各論の重要論点を210の設例に凝縮した、論文対策の入門に最適な演習書です。民法版と同様の「1問1見開き(1ページ設例、1ページ解説)」という構成を継 […]
AI要約:『ひとりで学ぶ会社法』の評価と特徴 本書は、その名の通り「独学」に特化し、演習を通じて会社法の複雑な制度を段階的にマスターできるように設計された実戦的な演習書です。 主な特徴とメリット 条文を引く習慣が身につく […]
AI要約:『基本刑法I 総論』の評価と特徴 本書は、現在の司法試験・予備試験対策において「受験生のバイブル」とまで称される、圧倒的シェアを誇る定番の基本書です。 主な特徴とメリット 試験対策に特化した構成: 学者による執 […]
法書ログの姉妹サイトです。
ジャンル
出版社

新着クチコミ
民事訴訟法の「深さ」を出す
早稲田ローの勅使河原先生の本です。
一時期司法試験の種本としても有名になりました。
内容としては既判力や二重起訴という基本概念の深堀が中心で網羅系の教科書というよりは予備試験の短答合格後の知識の補強に使用する副読本のような立ち位置だと思います。
特に固有必要的共同のその1は予備校教材では中々理解し難い部分を整理できるのでおすすめです。
続きを読む 閉じる
基本刑法の内容をより理解するための1冊
一通り刑法の基礎を学んだ後に読むと、総論の各論点についてより正確な理解ができるようになる。
自身の体験として、基本刑法1を読み、その時はある程度理解・記憶したと思っていた部分が、この本を読んで誤解していたことに気づいた。
全体の内容は、総論の中でも混乱しやすい部分を重点的に記載する形式なので網羅性自体はそこまでないため、基本刑法などの横に置いて辞書的に活用するのが良いと考える。
続きを読む 閉じる
伝聞はコレ
伝聞の予備校講義や動画を見るよりも、ストゥディア刑訴くらいの軽めの本でひと通りやったなら、あとはコレを読み、演習するのみ。こんなによく出来た本はない。
実務に出ても混乱したらこの本を読む。
続きを読む 閉じる
基礎基本
現在、東京大学で刑法を教えられている和田先生の本です。以前は慶應義塾でも教えられていました。
先生としては、この本に書かれている内容を理解できて、初めて刑法のスタートラインに立つことになるそうです。
学部1年生で扱う内容が主ですが、わかりやすい短文事例があり、中級者が復習をするのにはおすすめだと思います。
続きを読む 閉じる